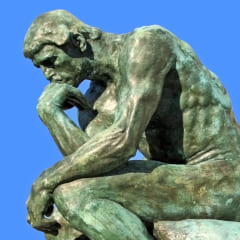五月病の症状・原因や、なりやすい人の特徴、うつ病との関係



5月のゴールデンウィーク明けごろに、なんとなく体調がすぐれず、やる気が起きず、授業や仕事に集中できない、学校や会社に行きたくない──そのような、いわゆる《五月病》は、もともとは受験で燃え尽きた大学生を対象に名付けられたものでしたが、今では世代に関係なく使用される傾向にある言葉です。
不調が数日のことなら、あまり心配する必要はありませんが、もし、数週間以上続くようであれば、《うつ病》や《適応障害》などを発症している可能性があります。うつ病を発症してしまうと本格的な治療が必要になってしまうため、そうならないためにも予防や早めの対処が大切です。
この記事では、五月病の症状・原因・予防や対処法、うつ病との関係などについて解説します。
五月病とは
《五月病(5月病)》は、5月のゴールデンウィーク明けごろに心身に現れる不調(ストレス症状)の総称です。医学的な用語ではなく、マスメディアが用いる言葉です。
もともとは、受験戦争を戦い抜いて合格した大学生が、入学後に目標を見失い、また新環境に対応できないことなどを背景にして、緊張が途切れる5月ごろにスランプにおちいって無気力な状態になることをいいました。
現在では、大学生に限らず、新社会人を含め、世代を限定せずに使用される傾向があります。
五月病自体は疾患名ではありません。しかし、これらのストレス症状の実体が《うつ病》や《適応障害》などである可能性があり、注意が必要な状態です。
五月病の症状
五月病では、心身にさまざまな症状が現れます。深刻さには個人差があり、重い場合は出勤や通学が難しくなることもあります。
五月病の精神症状
五月病の精神的な症状には以下のようなものがあります。
- やる気が出ない
- 気分が落ち込む
- イライラする
- 集中できない
- 記憶力・判断力の低下
五月病の身体症状
五月病の身体的な症状には以下のようなものがあります。
- 体がだるい、疲れが取れない
- 食欲がわかない
- 下痢・便秘
- 頭痛・肩こり
- めまい・耳鳴り
- 眠れない、夜中や朝早くに目が覚める
- 朝起きられない、日中眠い
五月病は医療機関にかかるべきですか?
五月病は、多くの場合は一時的なストレス症状と考えられ、ほとんどの場合は医療機関に行くべきというほどではありません。数日の間、少し調子を落とすだけなら特に心配な状態ではないでしょう。
しかし、不調が長引く場合はうつ病や適応障害を発症している可能性があります。気分の落ち込みや眠れないなどの症状が日常生活に支障をきたしているような場合は、医療機関に相談してください。特にこういった症状がいくつも2週間以上続いているような場合はうつ病の可能性があります。
うつ病は早期発見・早期治療が大切です。うつ病の疑いがある場合は、なるべく早めに精神科・心療内科を受診してください。
五月病の原因
五月病になる要因としては、次のようなものが考えられます。
進級・進学や就職などの転機
日本では、進学や進級、就職、配置転換や転勤などの区切りが4月であることが多く、この時季に職場・学校生活や人間関係などの環境が激変することも少なくありません。環境の変化はそのままストレスになります。
理想と現実のギャップ
高校までと大学では、学習への取り組み方が大きく変化します。また、学生から社会人への転換も同様です。これまでと完全に異なる世界に飛び込むときには、想像・期待していたものと現実とのギャップに大きなストレスを抱えがちです。
目標の喪失
受験戦争や就職活動を勝ち抜き一区切りがついたことで、一時的に目標を見失うことがあります。その状況下に、これまでと大きく異なる新しい世界に相対することから、大きなストレスを抱えることになります。
生活リズムの乱れ
5月にはゴールデンウィークがありますが、普段、仕事や学校があるときには規則正しく生活している人も、長期休暇中は夜更かし、朝寝坊から生活のリズムが乱れるということは珍しくないでしょう(特に帰省や旅行など長距離移動がともなうときにリズムを守り続けることは困難です)。睡眠時間が大きく乱れると食事時間や取り方も不規則になるうえ、栄養バランスも悪くなりがちです。
夏季うつ
不調が5月で終わらず、夏場まで続くことが毎年のように現れている場合は、夏型の季節性うつ病(夏季うつ)の可能性があります。《夏季うつ》は、夏に発症する季節性のうつ病で、《季節性感情障害(SAD)》の夏型です。夏の不調というと日本では夏バテが思い起こされますが、《夏季うつ》は反復性のうつ病のサブタイプ(下位分類)であり、夏バテとは比較にならないほど深刻な状態です。
-

夏季うつ病~「ただの夏バテ」ではない~
《夏季うつ病》は夏に発症する季節性のうつ病で、《季節性感情障害(SAD)》の夏型です。夏の体調不良の代表格「夏バテ」とは比較にならないほど深刻な状態であり、不眠、食欲減退と体重減少、不安や焦燥感などが目立ちます。夏季うつ病の症状・原因・対処法などについて解説します。

夏季うつ病~「ただの夏バテ」ではない~
《夏季うつ病》は夏に発症する季節性のうつ病で、《季節性感情障害(SAD)》の夏型です。夏の体調不良の代表格「夏バテ」とは比較にならないほど深刻な状態であり、不眠、食欲減退と体重減少、不安や焦燥感などが目立ちます。夏季うつ病の症状・原因・対処法などについて解説します。
五月病になりやすい人の特徴
次のような人は五月病になりやすいとされています。
- 環境が大きく変わった人
- 几帳面、真面目な人
- 責任感が強い人
- 悩みを一人で抱え込みがちな人
- おとなしい人
- 完璧主義
五月病の予防と対処法
ストレスはあって当然なものなので、ストレスとうまく付き合うことが五月病の予防や対策には重要です。
- 睡眠をしっかりとる:夜更かしや朝寝坊など、不規則な睡眠習慣は睡眠の質を低下させます。睡眠の質が落ち睡眠不足になることで、イライラしたり、集中力が落ちたりなど生活にいろいろと支障が出てきます。睡眠のリズムを守ることは快眠にとって非常に重要です。毎日同じ時間に寝て、毎日同じ時間に起きる習慣を身につけましょう。起床後はすぐに朝日を浴びましょう。
- バランスの良い食事をとる:毎日3回、栄養バランスの良いおいしい食事をとることは、健康的な身体の基礎となります。特に朝食は大切です。
- 適度に身体を動かす:身体を動かすことは、ストレス予防・解消や健康に大切な習慣です。日中にほどよく疲れることで、夜の睡眠の質改善にも役立ちます。しっかり運動することが難しい場合は、散歩をするなど、今より少しでも身体を動かすことを意識してください。興味があるイベントへの参加もいいでしょう。この時季は潮干狩りやネモフィラ祭り、御田植祭などが定番でしょう。
- リラックス時間を作る:読書をする、音楽を聴く、お気に入りの香りをかぐ、ゆっくりお風呂に入る、自然と触れ合うなど、リラックスした時間を過ごすことは、代表的なストレス解消法です。マッサージやストレッチなども効果的です。ストレスに疲れたときは、無理をせずに気分転換することも大切です。
- 悩みを打ち明ける:いろいろな異変を感じたときは、一人で悩まずに周囲に相談してください。話を聞いてもらうだけでも気分が落ち着くこともあります。家族や友人に打ち明けにくい場合は、専門的な相談窓口の利用も有効です。
五月病とうつ病は関係しますか?
うつ病と五月病は定義が異なり、同じものではありません。しかし、無関係とはいえません。
五月病と呼ばれる状態の中にうつ病や適応障害が混在している、あるいは五月病からうつ病や適応障害に発展してしまうという可能性は十分にありえます。
気分が落ち込む、趣味が楽しめない、眠れない、食欲がないなどの症状が2週間以上続いて日常生活に支障をきたしているような場合はうつ病を発症している可能性があります。そのような場合は医療機関に相談してください。「うつ病なのかな?」と心配なときには、セルフチェックをご利用ください。
うつ病は早期発見・早期治療が大切です。うつ病の疑いがある場合は、なるべく早めに精神科・心療内科を受診してください。
まとめ
《五月病(5月病)》は、5月のゴールデンウィーク明けごろに、心身に現れる不調(ストレス症状)の総称です。五月病は疾患名ではありませんが、《うつ病》や《適応障害》などが隠れている可能性があります。
五月病では、「やる気が出ない」「イライラする」「気分が落ち込む」などの精神症状に加え、「体がだるい」「頭痛・肩こり」「眠れない」などの身体的な症状が現れます。進学や就職などの急激で大きな環境変化に心身が追い付いていない状態であり、生活変化への戸惑いや目標の喪失、生活リズムの乱れなども要因となっていると考えられます。
五月病の予防と対策には、睡眠をしっかりとる、バランスの良い食事を毎日3食とる、適度に身体を動かす、などが有効です。また、読書や音楽鑑賞、入浴などリラックスできる時間を確保し、困りごとには一人で悩まずに周囲に相談することも大切です。
五月病は一時的なストレス症状と考えられますが、複数の症状が2週間以上続いて日常生活に支障が出ているような場合はうつ病を発症している可能性があります。そのような場合は医療機関に相談してください。

主要参考文献7 ソース
- 岡田尊司(2013)『ストレスと適応障害:つらい時期を乗り越える技術』, 幻冬舎
- 鈴木郁子(2023)『自律神経の科学:「身体が整う」とはどういうことか』, 講談社
- 中村真哉(編)(2023)『脳科学で解き明かす ストレスと脳の取扱説明書:科学的に正しいストレスの対応マニュアル』, (Newton別冊), ニュートンプレス
- 福間詳(2013)『ストレスのはなし:メカニズムと対処法』, 中央公論新社
- 松下正明(編)(2021)『不安または恐怖関連症群 強迫症 ストレス関連症群 パーソナリティ症』松下正明監修, (講座 精神疾患の臨床 3), 中山書店
- 山崎久美子(2005)「『五月病』とその周辺」, (五月病:環境の変化への支援), 『大学と学生』, 489, 8-16(参照:2024/7/16)
- 日本予防医学協会(2018)「環境の変化が引き起こす『五月病』とは?」, 『健康づくりかわら版』, 222(参照:2024/12/2)

品川メンタルクリニックはうつ病かどうかが分かる「光トポグラフィー検査」や薬を使わない新たなうつ病治療「磁気刺激治療(TMS)」を行っております。
うつ病の状態が悪化する前に、ぜひお気軽にご相談ください。