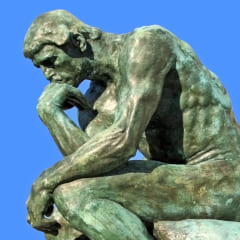アクチベーションシンドローム(賦活症候群)の症状、他害や自殺との関連



抗うつ薬の飲み始めや増量時に、不安やイライラ感、衝動性など、過剰な興奮が現れる症状を《アクチベーションシンドローム(賦活症候群)》といいます。アクチベーションシンドロームは潜在的な自殺リスクを持つ重大な副作用と考えられており、若年層への処方時には特に注意を要するとされています。
この記事では、抗うつ薬の副作用である《アクティベーションシンドローム》について、症状、他害や自殺との関連、対処法や双極性障害との関連などについて解説します。
アクチベーションシンドローム(賦活症候群)とは
《アクチベーションシンドローム》あるいは《賦活症候群(ふかつしょうこうぐん)》とは、抗うつ薬の副作用の1種で、薬の飲み始めや増量時に、中枢神経が過剰に活性化されて現れる症状の総称です。不安・焦燥感、攻撃性、衝動性、アカシジア(下半身がムズムズしてじっと座っていられない)などの症状が現れます。《ジタリネスシンドローム》といわれることもあります。
アクチベーションシンドロームは潜在的な自殺リスクを持つ重大な副作用と考えられており、若年層への処方時には特に注意を要するとされています。
アクチベーションシンドロームの症状
アクチベーションシンドロームは、特に抗うつ薬開始後2週間以内、あるいは増量時に生じやすいです。以下のような症状が現れます。
- 不安・焦燥感の増大
- 不眠
- パニック発作
- 易刺激性・敵意・攻撃性
- 衝動性
- アカシジア(下半身のムズムズ感やソワソワ感のため、じっと座っていられない症状)
- 軽躁・躁状態(気分が高揚する)
これらの症状は、うつ病をはじめ、他の精神疾患の症状としても現れるため、症状の悪化との判別が容易ではありませんが、服薬開始後や増量後に症状が出現する、あるいは悪化するような場合は、薬の影響が考えられます。
他害との関連
アクチベーションシンドロームの攻撃性や敵意は、他害につながる可能性がある症状です。
厚生労働省所管の医薬品医療機器総合機構(PMDA)は、他害行為を以下の3レベルに分類し、分析しています[1]。
- レベル0:具体的な他害を実行していない段階
- レベル1:暴言を吐く、カッとしやすくなるなど、傷害につながる可能性がある段階
- レベル2:殺人や傷害などの暴力行為を実行する段階
他害行為レベル0は、他害しようと考えることや計画をたてるまで、他害行為レベル1・2は他害を実行することです。
レベル別に集計・分析した結果からは、以下のような考察が得られています。
- 性別:レベル0の割合は女性が、レベル2の割合は男性が高い。
- 年齢:若い人ほど、レベルが高くなる傾向がある。
- 診断:《うつ病》と診断されている人はレベル2よりもレベル0の割合が高い。レベル0の割合はうつ病よりも《うつ状態》《不安障害》《強迫性障害》《双極性障害》のほうが低く、特に《うつ状態》《不安障害》《強迫性障害》はレベル2の割合がうつ病よりも高い。
- 併存症:《パーソナリティ障害》などの、他の精神疾患を併存している場合はレベルが高くなる傾向がある。
- 過去の衝動的行為:過去に衝動的行為がある場合、レベルが高くなる傾向がある。
自殺との関連
因果関係ははっきりしていませんが、アクチベーションシンドロームが現れるケースで、基礎疾患の悪化、自殺念慮、自殺企図などが報告されています。
我が国においては、24歳以下の患者に抗うつ薬を投与する場合には、自殺念慮・自殺企図のリスクを考慮し、患者の状態やその変化を注意深く観察するように注意喚起されています。
セロトニン症候群との違い
不安や焦燥感をともなう抗うつ薬の副作用には、《セロトニン症候群》もあります。
セロトニン症候群は、脳内のセロトニンが過剰に活性化することで、中枢神経系や自律神経系などの症状を引き起こす、抗うつ薬の代表的な副作用です。
セロトニン症候群は、不安・焦燥・興奮などの精神症状が特徴的で、高熱、発汗、下痢などの自律神経症状や、手や身体のふるえ、発作的な筋肉の収縮などの神経筋の症状をともないます。セロトニン症候群は重篤な副作用であり、特に高熱が生命にかかわりうる危険な症状です。
症状発現までの時間はアクチベーションシンドロームよりもかなり早く、数分から数時間以内に出現します。適切な処置を行えば、70%は発症後24時間以内に改善するといわれています。
アクチベーションシンドロームの対処法
アクチベーションシンドロームが疑われる場合は、原因と考えられる薬剤(抗うつ薬)を中止、あるいは減量します。
投薬開始時に現れた場合は中止、増量後に現れた場合は以前の容量に戻すという対応が一般的です。必要に応じて他の薬剤(抗不安薬、気分安定薬など)を追加処方する場合もあります。
いずれにせよ自己判断で中止したり、減量したりせずに、すみやかに医師に相談してください。
双極性障害との関連
アクチベーションシンドロームで出現する症状は《双極性障害》の症状と類似しており、若い年齢層に出現しやすいなど、双極性障害の特徴とも合致しています。治療中のアクチベーションシンドロームの出現は、双極性障害診断の指標となる可能性が指摘されています[2]。
もともと双極性障害の抑うつ状態と単極性のうつ病(普通のうつ病)を区別することは非常に困難です。それに加え、患者本人は躁状態・軽躁状態を「調子が良い」状態と判断しがちで、病気の症状としての自覚がありません。
さらに(特に双極性Ⅱ型障害では)患者はほとんど抑うつ状態で来院するため、過去の軽躁状態を診断することは非常に難しいということも関係しています。
光トポグラフィー検査
当院では、診断に客観的視点を加える《光トポグラフィー検査》を行っております。
光トポグラフィー検査は、近赤外光を用いて脳表層部の血流変化を測定する安全な検査です。この検査だけで診断できるわけではありませんが、《うつ病》と《双極性障害の抑うつ状態》を見分ける補助的情報として用いられます。
ほとんど副作用が無いTMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)
《TMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)》は、磁気を介して脳の特定部位を刺激することで、うつ症状を改善させる治療法です。TMS治療では患部(脳)を直接治療するため、副作用がほとんど無いことが大きな特徴です。副作用がつらくて薬物治療が続けられないという人には、TMS治療はおすすめです。
TMS治療では、自殺念慮や自殺企図などの副作用は報告されておらず、それらが心配な人にもおすすめです。
また、TMS治療は薬物療法とは異なるメカニズムでうつ病に働きかけるので、薬の効果が無い人にも有効である可能性があります。特に2剤目の抗うつ薬も効果が無かった場合は、TMS治療を試す価値は高いでしょう。
まとめ
《アクチベーションシンドローム(賦活症候群)》とは、抗うつの飲み始めや増量時に中枢神経が過剰に活性化されることで現れる副作用です。不安・焦燥感、攻撃性、衝動性、アカシジア(下半身がムズムズしてじっと座っていられない)などの症状が現れます。
アクチベーションシンドロームの攻撃性や敵意は、他者を物理的に傷つける可能性があります。女性よりも男性、高齢者よりも若い人の方が暴力を実行する傾向があります。
また、アクチベーションシンドロームは潜在的な自殺リスクを持つ重大な副作用と考えられており、24歳以下の若年層への処方時には特に注意を要するとされています。
アクチベーションシンドロームが疑われる場合は、原因と考えられる薬剤を中止、あるいは減量するのが一般的ですが、自己判断で中止したり、減量したりせずに、すぐに医師に相談してください。
アクチベーションシンドロームと《双極性障害》の関連性が指摘されており、診断が難しい双極性障害の診断の指標となる可能性があります。
当院では、《うつ病》と《双極性障害の抑うつ状態》を見分けるための補助的情報を得られる《光トポグラフィー検査》を実施しています。また、ほとんど副作用が無い《TMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)》を専門で行っています。TMS治療は、自殺念慮や自殺企図などの副作用は報告されておらず、それらが心配な人にもおすすめです。薬物治療がうまくいっていない人も、良くなることをあきらめずにご相談ください。


品川メンタルクリニックはうつ病かどうかが分かる「光トポグラフィー検査」や薬を使わない新たなうつ病治療「磁気刺激治療(TMS)」を行っております。
うつ病の状態が悪化する前に、ぜひお気軽にご相談ください。