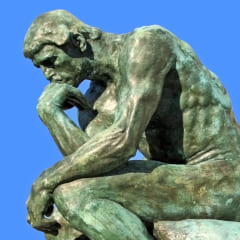『社交不安障害(あがり症・対人恐怖症)』とうつ病について



重要な取引のプレゼンテーション、意中の人との初めてのデート、第一志望の就職面接、人前でのスピーチ、授業中の発言、知り合いがいない飲み会やパーティへの参加──こういった場面で緊張するのは誰にでもある普通のことです。しかし、その緊張に制御できない不安や恐怖を感じるようなら、もしかすると《社交不安障害(あがり症・対人恐怖症)》を発症している可能性があります。
この記事では、社交不安障害(あがり症・対人恐怖症)の症状、原因、治療や対処、うつ病との関係などについて解説します。
社交不安障害(あがり症・対人恐怖症)の症状
社交不安障害では、他人に注目される可能性のある1つ以上の社交場面に対する著しい恐怖や不安を抱きます。この恐怖や不安は、その状況がもたらす現実的な脅威や危険とまったく釣り合っていません。社交不安障害の人は、この状況を回避しようとし、もしくは強い恐怖や不安を感じながら耐えています。
社交不安障害の症状には、以下のようなさまざまなものがあります。
社交不安障害(あがり症・対人恐怖症)の精神症状
社交不安障害の精神症状には以下のようなものがあります。
- 見知らぬ人との交流への強い恐怖・不安
- 否定されることへの恐怖・不安
- 恥ずかしい思いをしたり、屈辱的な思いをしたりすることへの恐怖・不安
- 他人の迷惑になっているのではないかという恐怖・不安
- 自分の恐怖心がさとられることへの恐怖・不安
- 赤面、発汗、手足や声がふるえるなどの身体症状が注目されることへの恐怖・不安
- 頭が真っ白になる
社交不安障害(あがり症・対人恐怖症)の身体症状
社交不安障害の身体症状には以下のようなものがあります。
- 赤面
- 動悸、息切れ
- 発汗
- 手足や声のふるえ
- 吐き気、下痢
- めまい
社交不安障害(あがり症・対人恐怖症)の行動面の症状
社交不安障害では、次のような行動がみられます。
- 注目されそうな状況を避ける
- パーティや社交行事への参加を避ける
- 話しかけることができない
- 目を合わせない
- 人がいる部屋に入れない
- 不登校や引きこもりになる
- 自意識過剰になる
- 話し声が小さい
人前であがってしまうときは受診すべき?
人前で緊張することは異常なことではありません。どんな場面でも全く緊張しないという人はまれで、それはそれでなんらかの問題がある可能性があります。多くの人は、不安や緊張があるからこそ、それを克服するために努力し、集中力を高めてチャレンジします。そうやって場数を踏んで慣れることは健全なプロセスです。つまり、緊張することは病気でもなんでもありません。何の心配もありません。
しかし、そういう場面を極端に恐れ、実際に避けてしまうような場合は、注意が必要です。社交的な場面への恐れが日常生活に影響を与えている場合は、医療機関を受診してください。
社交不安障害(あがり症・対人恐怖症)になりやすい人
社交不安障害の危険因子には以下のようなものがあります。
- 発症年齢は低年齢(主に10代ごろ)
- 家族歴
- 否定的な経験(からかいやいじめ、拒絶、屈辱などの体験)
- 気質・性格(恥ずかしがり屋、引っ込み思案)
社交不安障害(あがり症・対人恐怖症)の原因
社交不安障害は、(他の精神疾患と同じように)生物学的要因と環境的要因の複雑な相互作用から生じると考えられます。
- 遺伝:家族に社交不安障害患者がいる。
- 脳の構造:大勢の人前でスピーチをする課題中に、脳の《扁桃体》という部位の過活動が報告されています。また、写真による顔表情認知課題でも、否定的な表情(怒り、嘲笑など)の写真を見たときに扁桃体の過活動が報告されています。
- 環境:幼少期の虐待経験や困難。
社交不安障害(あがり症・対人恐怖症)の治療
社交不安障害の治療法は、主に《心理療法》と《薬物療法》によります。
心理療法
社交不安障害への代表的な心理療法としては《認知行動療法》や《森田療法》などがあげられます。
- 認知行動療法(CBT):《認知行動療法》は、人の心理面に働きかけることで、否定的な思考パターンを修正し、状態の改善を図る心理療法です。
- 森田療法:《森田療法》は、森田正馬医師が創始した我が国発祥の治療法です。不安や恐怖を、排除すべき特別なものではなく「自然な感情」として受け入れることで、不安にとらわれることなく、自分らしい生き方を実現しようという心理療法です。
薬物療法
社交不安障害での薬物療法では、《抗うつ薬》や《ベンゾジアゼピン系抗不安薬》が用いられます。
ベンゾジアゼピン系抗不安薬は即効性がありますが、耐性と依存の問題から短期間の処方が原則です。
社交不安障害(あがり症・対人恐怖症)への対処
ライフスタイルの改善は、社交不安障害をはじめとした不安症の発症予防や経過の安定につながります。
ライフスタイルの改善方法には、以下のようなものがあげられます。
- 質の良い睡眠をしっかりとる
- 定期的に休養し、疲れを取る
- 適度に運動する
- アルコールやカフェインを控える
- 家族や友人のサポートを受ける
社交不安障害(あがり症・対人恐怖症)と併存しやすい疾患
社交不安障害は、気分障害(うつ病や双極性障害など)の併存率が高く、ある調査研究によると、社交不安障害の33.4%がうつ病を併発し、気分障害全体では55.0%も併発したとのことです[1]。
また、多くの場合、社交不安障害がうつ病の前に発症します。
パフォーマンス限局型ではない社交不安障害では、しばしば《回避性パーソナリティ障害》が併存します。
うつ病との併存
前述の通り、社交不安障害とうつ病は高い割合で併存することがわかっています。
重いうつ病と不安症が併存している場合は不安症の治療がうまくいかないことも多く、基本的にはうつ病の治療を優先します。
不安症状だけではなく、気分の落ち込みを感じるようなら、うつ病を発症している可能性があります。
不安症が併存したうつ病へのTMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)
不安障害が併存するうつ病患者への《TMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)》の効果を分析した調査があります。この調査では、不安障害の併存の有無は、うつ病患者への治療効果に差がない(つまり、効果が期待できる)と報告しています[2]。TMS治療は、磁気による誘導電流で脳の特定部位を刺激する、副作用がほとんど無いうつ病治療です。
まとめ
《社交不安障害》は不安症の1つで、人前で何かを行うときの不安・恐怖や緊張が、過剰に強すぎるものです。《あがり症》や《対人恐怖症》は、多少の差異はあるものの、社交不安障害とおよそ同じものです。
社交不安障害の人は、人前での会話や書字、初対面の人との面談、公共の場での飲食など、一般的に不安や恐怖を感じることのない場面でも強い不安や恐怖を感じます。恐怖の対象は、同級生や同僚のように中間的な人間関係の人であり、親しい人や完全に無縁な人は怖くありません。ただの人混みではあまり緊張せず、中途半端な知り合いがいるときに緊張します。
社交不安障害は、否定されることへの恐怖心や、恥ずかしい思いをしたり、屈辱的な思いをしたりすることへの心配などから、赤面、発汗、手足や声のふるえなどのさまざまな身体症状が現れます。行動面でも他者に話しかけられない、アイコンタクトできないなどの問題が生じ、不登校や引きこもりにいたる場合もあります。
低年齢(主に10代ごろ)に発症しやすく、否定的な経験や消極的な性格なども社交不安障害の危険因子となります。
社交不安障害の治療法は、主に《心理療法》と《薬物療法》によります。うつ病が併存していることも多く、《TMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)》が選択されることもあります。TMS治療は副作用がほとんど無いことが特徴です。
社交的な場面への恐れが日常生活に影響を与えている場合は、医療機関の受診を検討してください。


品川メンタルクリニックはうつ病かどうかが分かる「光トポグラフィー検査」や薬を使わない新たなうつ病治療「磁気刺激治療(TMS)」を行っております。
うつ病の状態が悪化する前に、ぜひお気軽にご相談ください。