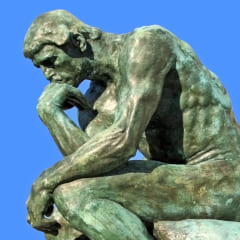パニック障害の症状・原因・治療法



《パニック障害》とは、予期しない《パニック発作》の再発を特徴とする精神疾患です。パニック発作は、激しい恐怖の中で、動悸、息苦しさ、死の恐怖などの複数の症状が現れ、短時間で治まる発作です。
パニック障害では、「また、あの発作が起きたらどうしよう」と将来の発作を過剰に心配するようになり、外出などの行動が制限されるようになります。
この記事では、パニック障害の症状・原因・治療法などについて解説します。
パニック障害とは
《パニック障害》もしくは《パニック症》とは、予期しない《パニック発作》の再発を特徴とする《不安障害(不安症)》です。不安障害は、何かに対する過剰な不安や恐怖が、日常生活に支障をきたす精神疾患の総称です。パニック発作は激しい恐怖の中で、動悸、息苦しさ、死の恐怖などの症状が現れ、短時間で落ち着く発作です。
パニック障害は、パニック発作の再発が不安や恐怖の対象です。パニック発作が何度も繰り返し現れることで「あの発作がまた起きたらどうしよう」と過剰に心配になり、外出ができなくなるなど行動が制限されるようになり、日常生活に大きな支障をきたします。学校や仕事に行けなくなることもあります。
パニック障害の症状
パニック障害の症状は、《パニック発作》《予期不安》《行動変化》の3つに分類されます。
パニック発作
《パニック発作》は激しい恐怖の中で、動悸、息苦しさ、死の恐怖などの症状が現れ、短時間で落ち着く発作です。パニック発作固有の症状ではなく、多くの精神疾患に共通する症状です。
アメリカ精神医学会(APA)の基準によると、パニック発作では以下の13の症状のうち4つ以上が現れるとされています。
- 動悸、心拍増加
- 発汗(冷や汗)
- 身体や手足のふるえ
- 息切れ、息苦しさ
- 息が詰まる感じ
- 胸の痛みや不快感
- 吐き気、腹痛、下痢
- めまい、ふらつき、気が遠くなる感じ
- 寒気、火照り
- しびれ、うずき感
- 非現実感、離人感(自分が自分でない感じ)
- 正気や自制を失う(気が狂う)ことへの恐怖
- 死への恐怖
通常、症状は数分(多くは10分以内)でピークに達し、症状が落ち着いたあとに、疲労感・倦怠感を感じることがあります。1回の発作は数分から30分、長くても1時間以内に自然に消失します。
パニック発作は不快な症状ですが、生命を脅かすような危険なものではありません。
パニック障害のパニック発作は、繰り返し予期されないタイミングに生じます。発作の頻度は、月に数回から1日に数回まで、重症度によって異なります。
「予期されない」とは、明らかなきっかけや前ぶれがない場合のことです。くつろいでいるときや、夜間眠っているときなど、周囲の状況とは無関係に起こります。
反対に「予期される」とは、明らかなきっかけがあるような場合のことです。例えば、犬に吠えられて発作を起こすような場合、これは「予期される」パニック発作です。
パニック障害では、予期されないパニック発作だけではなく、予期されるパニック発作が生じることもあります。欧米では、パニック障害患者の半数が、予期されないパニック発作と予期されるパニック発作の両方をもっています。予期されるパニック発作があるからパニック障害ではない、ということはありません。
予期不安
「また発作が起こるのでは」という発作再来に対する過度の不安・心配を《予期不安》といいます。発作の望ましくない結果(転倒、失禁、正気を失うなど)に対する不安・心配も含みます。
行動変化
《行動変化》とは、パニック発作のダメージを最小限にする、または避けるために行動を変化させることです。行動変化には、運動を避ける、不慣れな状況を避ける、パニック発作に備えて生活を再編するなどがあり、また次に述べる広場恐怖型の状況回避を含みます。
パニック障害の広場恐怖
《広場恐怖》とは、単に「広場が怖い」という意味ではなく、パニック発作が起きても助けを求めることができない状況や、すぐに逃げ出せない場所を避けるようになることです。「発作が出ると逃げられない」という不安で、行動が制限されるようになるということです。
具体的には、電車・バス・飛行機などの公共交通機関、トンネル・エレベーターの中・窓のない部屋などの閉鎖空間、美容院・歯医者・病院での検査・行列に並ぶなどの束縛された環境などがあてはまります。
パニック障害と季節性
パニック障害は、春と夏に発症しやすいという報告があります。パニック障害の症状は8月と12月に悪化することが多いとのことです[1]。
パニック障害は受診すべき?
パニック障害は回復が期待できる精神疾患です。早期に適切な治療を行うことで治りやすいといわれています。
パニック障害は、予期せぬパニック発作を複数回繰り返し、予期不安や行動変化が1ヶ月以上続くことで診断されるものですが、わざわざ2回目の発作や、1ヶ月症状が続くことを待つ必要はありません。一度でも発作が起き、そのことが心配な場合は、遠慮せずに医療機関を受診してください。
パニック障害の原因
パニック障害の原因は明らかではありませんが、複数の要因が積み重なることで脳の機能異常が起きていると考えられています。遺伝的な要因よりも、環境の影響が大きいとされています。
- 気質要因:否定的感情と不安への過敏さは、パニック発作出現の危険要因です。
- 環境要因:小児期の虐待は、他の不安障害よりもパニック障害患者で報告が多いとされています。喫煙やカフェイン(コーヒー、緑茶、紅茶、チョコレート、エナジードリンクなど)摂取はパニック発作の危険要因です。ほとんどの人は、発症前の数カ月間になんらかのストレス要因があったと報告しています。
- 遺伝要因:複数の遺伝子が、パニック障害のなりやすさに関連していると考えられています。親が不安障害や気分障害の場合、パニック障害のリスクが高まります。
- 生物的要因:脳の《扁桃体》という部位の機能不全が、パニック発作やパニック障害に関係していると考えられています。
パニック障害になりやすい人
パニック障害は、10代後半から成人初期に始まることが多く、男性よりも女性の方が2倍発症しやすいとわかっています。また、次のような経験、行動、習慣がある人は、発症リスクが高まります。
- パニック発作やパニック障害の家族歴
- 幼少期の虐待経験
- 性的暴行や大事故などのトラウマ体験
- 家族の死や重病など、人生における大きなストレス
- 離婚や出産など、人生における大きな変化
- 喫煙、カフェインの過剰摂取
パニック障害の治療
パニック障害の治療法は、主に《心理療法》と《薬物療法》によります。さらに最近は、《TMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)》がパニック障害に有効であるという報告もあります。
心理療法
パニック障害への心理療法では、主に《認知行動療法(CBT)》が用いられます。認知行動療法は、人の心理面に働きかけることで、否定的な思考パターンを修正し、状態の改善を図る心理療法です。
パニック障害では、胸の痛みや息苦しさというような身体症状を、「胸がどきどきする→心臓発作で死ぬ」「息がはあはあする→呼吸困難で死ぬ」と破滅的に解釈して強い恐怖を感じていることがあります。認知行動療法は、このような考え方を修正するものです。
薬物療法
パニック障害への薬物療法では、《抗うつ薬》や《ベンゾジアゼピン系抗不安薬》が用いられます。
抗うつ薬は、主にSSRIが用いられます。抗不安薬は即効性がありますが、耐性と依存の問題から短期間の処方が原則です。
TMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)
パニック障害と併存しやすい疾患
パニック障害は、気分障害(うつ病や双極性障害など)の併存率が高く、ある調査研究によると、パニック障害の33.4%がうつ病を併発し、気分障害全体では57.6%と過半数が併発、広場恐怖を伴うパニック障害では39.0%がうつ病を併発、気分障害全体では68.3%と3分の2が併発したとのことです[4]。
パニック障害とうつ病
前述の通り、パニック障害とうつ病は非常に併存しやすい精神疾患です。また、パニック発作自体は、パニック障害に限らず、うつ病でも起こるものです。不安症状が顕著なうつ病もあります。
気分が落ち込む、趣味などが楽しくなくなったなどの症状がある場合はうつ病の可能性があります。
パニック発作のすべてが病気とは限りません。例えば、あなたがクマに襲われたときにパニック発作が出たとしても、それは正常な反応の範囲内です。しかし、発作が正常かどうかわからず心配なときに医療機関にかかるというのは間違った判断ではありません。結果として問題ないと判明すればあなたの心配が1つ解消されますので、医療機関にかかるかどうか迷っているのなら、セルフチェックの結果に関係なく受診することをおすすめします。
なお、パニック障害に併存しやすいうつ病は、従来のうつ病よりも、《非定型うつ病》が多いとの指摘もあります。非定型うつ病は、過眠・過食・拒絶過敏性などが特徴的なうつ病のサブタイプ(下位分類)です。非定型うつ病について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
-

非定型うつ病の特徴と7つの症状
《非定型うつ病》は、世間の人の《うつ病》の一般的なイメージからかけ離れた症状をもつことから、仮病を疑われたり、怠けているだけではと誤解されたりしがちなうつ病です。この記事では主に従来のうつ病との違いに焦点を置き、非定型うつ病の特徴や症状などを解説します。

非定型うつ病の特徴と7つの症状
《非定型うつ病》は、世間の人の《うつ病》の一般的なイメージからかけ離れた症状をもつことから、仮病を疑われたり、怠けているだけではと誤解されたりしがちなうつ病です。この記事では主に従来のうつ病との違いに焦点を置き、非定型うつ病の特徴や症状などを解説します。
不安症が併存したうつ病へのTMS治療
不安障害が併存するうつ病患者へのTMS治療の効果を分析した調査があります。この調査では、不安障害の併存の有無は、うつ病患者への治療効果に差がない(つまり、効果が期待できる)と報告しています[5]。
まとめ
《パニック障害》とは、予期しない《パニック発作》の再発を特徴とする精神疾患です。パニック発作は、激しい恐怖の中で、動悸、息苦しさ、死の恐怖などの症状が現れ、短時間で治まる発作です。
パニック障害の症状は、《パニック発作》と《予期不安》《行動変化》の3つに分類されます。
パニック障害では、予期しない《パニック発作》が何度も繰り返します。《予期不安》は「また発作が起こるのでは」という発作再来に対する過度の不安・心配で、《行動変化》は、発作を回避するために、運動や不慣れな状況を避けたりします。行動変化には、パニック発作が起きても助けを求めることができない状況や、すぐに逃げ出せない場所を避けるようになる《広場恐怖》を含みます。
パニック障害の原因は明らかではありませんが、気質・環境・遺伝など複数の要因が積み重なることで、脳の機能異常が起きていると考えられています。パニック障害は、10代後半から成人初期に始まることが多く、女性の方が男性よりも発症しやすいことがわかっています。
パニック障害の治療は、主に《心理療法》と《薬物療法》によります。さらに最近は、《TMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)》がパニック障害に有効であるという報告も増えています。
パニック障害とうつ病は非常に併存しやすい精神疾患です。気分が落ち込む、趣味などが楽しくなくなったなどの症状がある場合はうつ病の可能性があります。
パニック障害にせよ、うつ病にせよ、日常生活に支障が出ているようなら、医療機関にご相談ください。


品川メンタルクリニックはうつ病かどうかが分かる「光トポグラフィー検査」や薬を使わない新たなうつ病治療「磁気刺激治療(TMS)」を行っております。
うつ病の状態が悪化する前に、ぜひお気軽にご相談ください。